秀吉の天下統一(1590年)後、家康は関東に移封され、三河には豊臣家臣の大名が移ってきた。
岡崎城) 田中吉正 吉田城(豊橋市)) 池田輝政
あまり知られていないが、現在の形で街が整備されたのがこの時代である。
しかし関ヶ原の戦い(1600年)で勝利した徳川家康が江戸幕府を開くと(1603年)、三河出身の徳川家譜代は大名として日本全国に散った。一方、三河は親藩や譜代大名領、さらに天領や旗本知行地に分割された(吉良上野介は旗本として先祖伝来の地である吉良町(西尾の隣)に領地を持っていた)。江戸時代の主な藩は以下の通りである。
挙母藩(豊田市)2万石 岡崎藩5万石 西尾藩6万石
吉田藩(豊橋市)7万石 田原藩3万石
三河には古くから国内の東西を貫く形で東海道が通っていたが、平和となったこの時代にはそのメリットが増加した。しかし
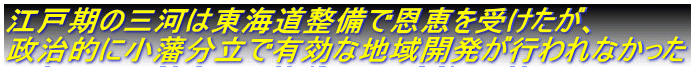 。特に西三河は矢作川の氾濫に対し各藩で一致した対策が採られず、発展が阻害された。
。特に西三河は矢作川の氾濫に対し各藩で一致した対策が採られず、発展が阻害された。
明治維新による廃藩置県により三河は尾張と共に「愛知県」となった(1876年)。 戦後、三河はトヨタ自動車の本拠地として工業が集積して大きな発展を遂げ、名古屋大都市圏の一角を占めることになる。
ここでは三河の歴史について述べる。
一般的に、団結心の強い徳川家臣団のイメージからか、
三河全体の気質や文化(三河弁も含めて)が画一的なものとして捉えられているきらいがある。しかし私も住んでみて分かったのだが、
三河の中でも山間部、平野部、沿岸部と様々である。とりわけ

。作家・
宮城谷昌光(蒲郡出身)は、折に触れてそのことを歴史に絡めて語っているが、ここでの試みもそれと軌を一にしている。
西三河(豊田・岡崎など)と東三河(豊橋など)では違いが大きい要因の最たるものが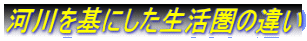
である。
古代律令制下でも、当初は西三河のみが「
三河国」で、東三河は「
穂国」だったという(通説による)。その後奈良時代中期に両者を統合したが、中心地たる
国府は東三河の豊川市に置かれた。畿内との交通を考えれば、三河湾の海上交通の要衝である豊川付近が便利だったようだ。
平安末期の源平の戦いに際しては、
三河の勢力は源頼朝に味方した。とりわけ既に前世紀から三河各地に勢力を持っていた
足利一族の働きは目覚しく、
足利氏は代々三河守護の地位を占めた。鎌倉期には足利氏の本家は関東にあったが、分家は三河で守護や地頭を務め、勢力を拡大した。意外かもしれないが、
細川、
今川、
吉良といった氏族はこの地で誕生した足利氏の分家である。
足利尊氏が
室町幕府を開くに際し、、三河の足利諸家が中心戦力となって貢献し、多くは幕府高官となって京都に進出した。
室町期の
三河の守護大名は当初は
一色氏、後に
細川氏に交代した(守護所は岡崎市北部と推定)。しかし足利家の地盤であっただけに、
在地の豪族は直接幕府高官と結びつく者も多く、守護権力が弱いままだった。こうして
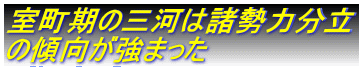
。なお
松平氏は室町初期に西三河の
松平郷(
豊田市東部の山中)にその姿を現し、幕府高官(政所執事)の
伊勢氏の被官となることで勢力を拡大したという(京都周辺の戦いにも参加した)。
戦国時代になると、三河の分立傾向は一層激化した(左上の図5.3参照)。
当初は吉良氏が西三河沿岸部を中心に遠江までうかがうほどに
勢力を誇ったが、一族が二派に別れて争ううちに衰微する。
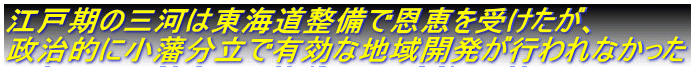 。特に西三河は矢作川の氾濫に対し各藩で一致した対策が採られず、発展が阻害された。
。特に西三河は矢作川の氾濫に対し各藩で一致した対策が採られず、発展が阻害された。
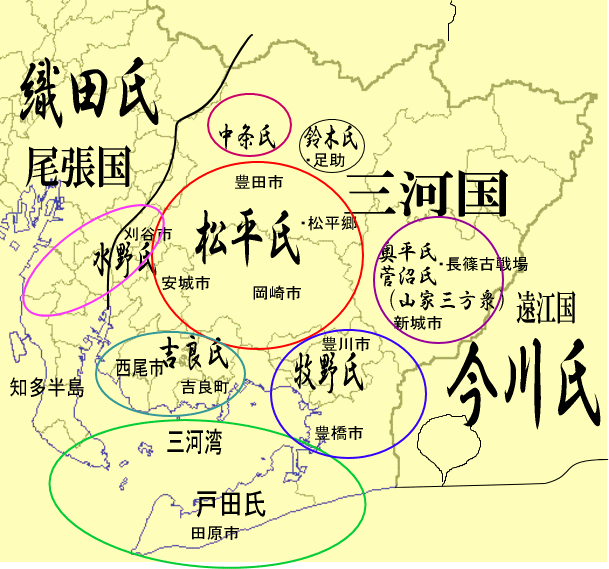
 次のページへ
次のページへ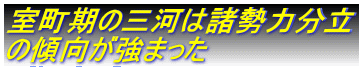 。なお松平氏は室町初期に西三河の松平郷(豊田市東部の山中)にその姿を現し、幕府高官(政所執事)の伊勢氏の被官となることで勢力を拡大したという(京都周辺の戦いにも参加した)。
。なお松平氏は室町初期に西三河の松平郷(豊田市東部の山中)にその姿を現し、幕府高官(政所執事)の伊勢氏の被官となることで勢力を拡大したという(京都周辺の戦いにも参加した)。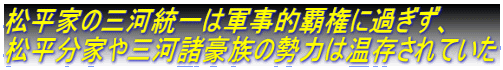 のである。諸豪族は後に徳川譜代の大名となるものが多く含まれていたが、当時の立場は松平氏と対等だった。結果、1535年に清康が暗殺されると、諸家はあっという間に離反したのである。特に牧野氏はすぐに今川方に付き、吉良氏や戸田氏は自立化行動をとった後、今川に屈服した。1540年代後半に今川氏は再び三河に進出し、松平氏も傘下において、三河での勢力を確立した。
のである。諸豪族は後に徳川譜代の大名となるものが多く含まれていたが、当時の立場は松平氏と対等だった。結果、1535年に清康が暗殺されると、諸家はあっという間に離反したのである。特に牧野氏はすぐに今川方に付き、吉良氏や戸田氏は自立化行動をとった後、今川に屈服した。1540年代後半に今川氏は再び三河に進出し、松平氏も傘下において、三河での勢力を確立した。



