次に②江戸の武士の言語は とまとめられる。ここで寛政元年(1789年)に起こったある争論の裁判記録における、吟味御留役人・星野鉄三郎の台詞を紹介する。(春原『近世庶民法資料 第二輯』所収)。「~候(そうろう)」など文語表現に混じって、下のような口語表現が見受けられる。
とまとめられる。ここで寛政元年(1789年)に起こったある争論の裁判記録における、吟味御留役人・星野鉄三郎の台詞を紹介する。(春原『近世庶民法資料 第二輯』所収)。「~候(そうろう)」など文語表現に混じって、下のような口語表現が見受けられる。
「さあそふてあろふ」
「ちよと申聞せ候ほとのことハしそふな事それもしないか」
「夫(それ)は違ふわさ、是は何ンてもなき事たぞよ」
「あいつ一向いけないやつた」
これを見ると、「~であろう」などいかにも時代劇の武士の言葉といった感じを受けるが、今の東京語と同じ特徴が多い。少なくとも江戸中期までは、上中級の武士の間でも荘重さを出すために、「~じゃ」「~ぬ」など上方語的な話し方が多く用いられたらしい。それは当時の戯作など文学作品での武士の話し方から伺える。その理由は、江戸には全国から人が集まるだけに通じやすく、かつ権威を備えた言語が必要されたためであろう(ただしアクセントは「甲種」と呼ばれる関西式アクセントではなく、「乙種」と呼ばれる東京式アクセントと思われる)。
しかしこの頃(18世紀終盤)ぐらいになると、「関東弁的な基盤の上に、京都語の特徴を部分的に取り入れた言語」として「江戸語」が確立したらしい。「江戸語」はこの頃(寛政年間)から、京都語に変わって「全国共通語」と扱われるようになったことが、各地で編纂された方言辞書の研究から明らかになっている。これより前に18世紀半ばには、いくつかの随筆に「江戸はかつて荒々しい土地だったが、京都の風俗を学び、昔と様子が変わった」「江戸は今や大都会となり、その言語も都会的になった」と書かれている(『標準語の成立事情』より)。象徴的なのは「~だろう」である。「~(だ)べい」を用いるのが在来の関東弁だが、江戸では上方語の「~じゃろう」をブレンドすることでこのような言い回しを完成し、「都会語」としての体裁や評価を備えていったようである(「~だろう」はこの時期以降の戯作物で江戸言葉として頻出するようになる。もっとも「~(だ)べい」もわずかながら用いられている)。これが後に「山の手言葉」につながり、共通語の基盤となる。
ところで上の文例で「~わさ」「~だぞよ」など異質な特徴もあるが、これがひょっとしたら江戸初期から武士の間で受け継がれた三河弁の名残りかもしれない。
最後に③江戸庶民の言葉だが、初期においては「ベーベー言葉」が話されていた事は何度も述べた。それを遊侠の徒と化した旗本がことさらに粗野な言葉として取り入れることで"六方詞(ことば)”という言葉が出来上がった。これは文学作品でも取り入れられたが、下は六方詞で読んだ雑俳である。
「わんざくれ ふんばるべいか 今日ばかり あすはからすが かっかじるべい」
しかし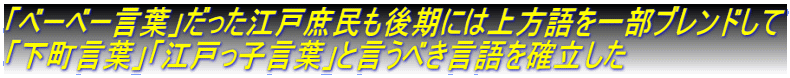 ようだ。それは「べらんめえ調」とも呼ばれ、多少関東土着の粗野さを残しているが、「くだけた都会語」との体裁を備えて、文学作品にも取り入られるようになった。この背景には、社会の上層を占める武士のことばの影響を受けたということがあったと思われる。次は、定番的に引用される式亭三馬(『浮世風呂』で著名)の言葉である。。
ようだ。それは「べらんめえ調」とも呼ばれ、多少関東土着の粗野さを残しているが、「くだけた都会語」との体裁を備えて、文学作品にも取り入られるようになった。この背景には、社会の上層を占める武士のことばの影響を受けたということがあったと思われる。次は、定番的に引用される式亭三馬(『浮世風呂』で著名)の言葉である。。
「ハテ江戸訛といふけれど。おいらが詞(ことば)は下司下郎で。ぐっと鄙(いや)しいのだ。正真正銘の江戸言といふは。江戸でうまれたお歴々のつかふのが本江戸さ」
最後にこの時代の江戸の下級武士の貴重な言語資料を紹介する。勝小吉(勝海舟の父)の『夢酔独言』である(引用は『近世武家言葉の研究』より)。
「おれは今までもなんにも文字のむづかしい事は読めぬから・・」
「能く々々不法もの馬鹿者のいましめにするがいいぜ。」
勝小吉はある程度教養がありながら、子孫に語り聞かせるために、あえて話し言葉そのままの文章を綴ったとのことである。ためにこの時代の江戸庶民やそれに近い下級武士の言語実態を示す貴重な資料が残ったわけである。このような言葉の系譜は、息子・勝海舟が明治になって語った回想録『氷川清話』に受け継がれた。
さて、以上から「三河弁と東京語の関係」について次のような結論が出せる。
![]()
![]()
この話題について、これでひとつの区切りが出せたと思われる。
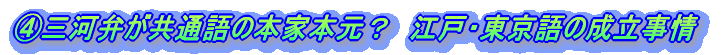
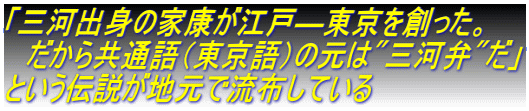 ということである。
ということである。 。東京語では進行形は「~てる」、否定形は「~ない」である(「~じゃん」のみは共通語として扱われるようになったが)。なのに三河弁が東京語の基とは本当であろうか。
。東京語では進行形は「~てる」、否定形は「~ない」である(「~じゃん」のみは共通語として扱われるようになったが)。なのに三河弁が東京語の基とは本当であろうか。 のだろう。しかしこれは武士についてだけで、庶民層は従来の「ベーベー言葉」的な関東方言を用いていただろう。このような江戸の言語状況はその後どういう展開を見せたか。 これについて述べるには、3つの階層別に分けて考えねばならない。すなわち、
のだろう。しかしこれは武士についてだけで、庶民層は従来の「ベーベー言葉」的な関東方言を用いていただろう。このような江戸の言語状況はその後どういう展開を見せたか。 これについて述べるには、3つの階層別に分けて考えねばならない。すなわち、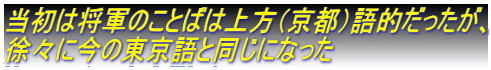 となる。まず10代将軍・家治の談話に「所労も全快て一段な義じや」「滞りもなふて(のうて)」など例がある。これを見ると、断定の「~じゃ」、ウ音便の「のうて(=なくて)」など当時の公用語だった上方語(京都語)的な特徴が見られる。幕府も4代家綱以降、京都の風俗を取り入れるのに熱心になり、江戸城内の生活がどんどん京都化していったと言われる。言語もその一環だったようだ。
となる。まず10代将軍・家治の談話に「所労も全快て一段な義じや」「滞りもなふて(のうて)」など例がある。これを見ると、断定の「~じゃ」、ウ音便の「のうて(=なくて)」など当時の公用語だった上方語(京都語)的な特徴が見られる。幕府も4代家綱以降、京都の風俗を取り入れるのに熱心になり、江戸城内の生活がどんどん京都化していったと言われる。言語もその一環だったようだ。





 5の先頭ページへ戻る
5の先頭ページへ戻る