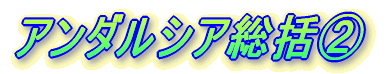ところでこのように独自性の強いアンダルシアだが、バルセロナなどカタルーニャ地方やバスク地方で見られるような「反中央」という意識は弱い。むしろアンダルシア人がマドリードに多く移住するなど親和的だといっていい。
スペインにおいては地元意識はサッカーチームの応援に反映される。セビーリャにおいても、セビーリャFC(チームカラーは白に赤)、さらにベティス(緑)という2つの名門チームがあるが、その応援が「反中央=反レアル・マドリード」とはなることはない。むしろ地元のライバル同士の対決(ダービーマッチ)で激しく対抗心が燃え上がる。
アンダルシア人はこのように独自性の強い地元に誇りを持ちながらも中央に対して親和的な態度をとる。その理由はアンダルシアがスペインにとって新開地だったことが関係しているのだろう。
レコンキスタによる征服後、大勢の北方人がこの地方に入植してきた。それはそれまでのアンダルシアの特徴を洗い流すものだった。
こうしたことから現在のアンダルシアは「スペイン語圏」となっている。しかしそのスペイン語はマドリードで話される「標準語」とは異なる。
私はバルの30代ぐらいの店員に世間話のついでという感じに
「セビーリャのスペイン語はマドリードと違うと言うが、どう違うんだい?」
と英語で聞いてみた。すると店員は
「アーハッハハハ!!」
とばかりに大笑いした。旅行者、しかも日本人が自分達の卑近な日常語に興味を持つ意外性に思わず笑ってしまったのだろう。
店員氏は「ちょっとだけね。まあ、どう違うかは言語学者じゃないから分からないよ(笑)」と言った。
結局質問の答えは得られなかったが、翌日駅で女性職員が
「ブエノ・ディア」
と言った場面に遭遇した。標準語では「ブエノス・ディアス(こんにちは)」である。帰国後に専門書を読むと
「アンダルシア方言の特徴は語末のsを省略すること」
と書いてあった。他に「グラシアス(ありがとう)」も「グラシア」と言うらしい。他地方のスペイン人が
「アンダルシア人はsを食べる」
と揶揄する話も載っていた。ちなみにアンダルシア人は中南米に多く移民したので、これらの地域のスペイン語はアンダルシア方言の影響が強いらしい。
こうして多くの有意義かつ愉快なアンダルシア体験を終えて、私はマドリードに向かった。