 |
| 多治見市郊外の浄光寺付近で流れる土岐川。東美濃西部の主要河川である。 |
3.3
 |
| 多治見市郊外の浄光寺付近で流れる土岐川。東美濃西部の主要河川である。 |
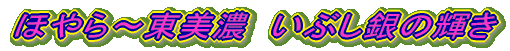
目次
(1)東美濃ってどんな所? ~場所とことばのPoint~ ①② ③
| 図表3.6 :東美濃 全容地図 |
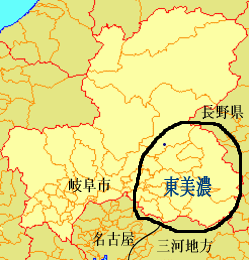 |
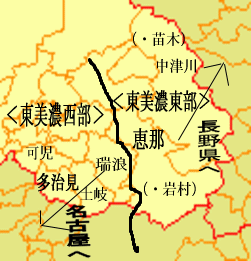 |

 |
| 東美濃の玄関口にして最大の都市 (人口11万人)多治見の駅前の光景 |
~場所とことばのPoint~


この節では、東美濃地方の方言について書いていく。とは言え、「それどこ?」という人が多いだろう。
「東美濃地方」とは、岐阜県の南東部、旧・美濃国の東部である(左地図参照)。3.1で述べたように、可児 多治見 土岐 瑞浪 恵那 中津川 などの市から成る。通常の定義では可児は含まれないのだが、このページでは含めることにする。ところで「東美濃」とはあまり耳慣れない地名だろう。通常は「東濃(とうのう)地方」と言うが、東海以外の地方の人にも分かるように、このように呼称する。
とは言え、どんな地方なのかイメージできない人が大半のはずだ。岐阜県といえば、一般的には岐阜市を中心とする「西美濃」のイメージが強い。「西美濃」は『国盗り物語』や「関が原の合戦」といった華やかな戦国絵巻の舞台だったし、現代も芸能界などに岐阜市など西美濃の出身者は多い。「東美濃」も、女子アナウンサーの近藤サト(土岐市)や草野満代(中津川市)などはいるが、どうしても地味な印象がぬぐえない。
しかしここもあまり知られていないが、戦国史の興味深い舞台なのである。地理的には「尾張・西美濃」と「信州」に挟まれており、「織田」と「武田」がせめぎ合った地域である。桃山時代以降全国に知られた![]() はここである(現代でも陶器生産のシェア50%を占める)。江戸時代には「中山道」という主要街道が通り、宿場町が多く営まれた。
はここである(現代でも陶器生産のシェア50%を占める)。江戸時代には「中山道」という主要街道が通り、宿場町が多く営まれた。![]() というべき地域である。
というべき地域である。
また![]() とされているのはここであり、地元では「東京から東濃へ」をキャッチフレーズにアピールに努めている。言語的にも、「西美濃」とはやや異なる独自の特徴を持っている。その興味深い「東美濃」のことばと地域について、ここで紹介する。
とされているのはここであり、地元では「東京から東濃へ」をキャッチフレーズにアピールに努めている。言語的にも、「西美濃」とはやや異なる独自の特徴を持っている。その興味深い「東美濃」のことばと地域について、ここで紹介する。
※ 図表3.7: 東美濃の下位区分
| 東美濃西部 | 可児 多治見 土岐 瑞浪 |
| 東美濃東部 | 恵那(旧・岩村、明智の両町を合併) 中津川 |
では三河との関係はどうなのか?結論から言うと、「三河との関係はあまり強くない」のである。もちろん隣接しているので、関係が無くは無いのだが、関係が深いのは三河と接する岩村や明智(共に現・恵那市)など東美濃東南部だけである。この付近のみ、断定の語尾が「~だ」であり、「ほだらー」など三河弁と同様の方言が聞かれる。他の地域が全て「ほやらー」と言う中で、これは特徴的である。三河との関係についてはこれだけである。(※)
では「~やらー」はどこからの影響と考えればよいか?
それは信州(長野県)とのつながりによるもの、と考えるべきである。とは言ってもにわかに納得できないだろう。例えば断定の語尾において、東日本的な「~だ」を使う信州と、西日本的な「~や(かつては「~じゃ」)」を使う東美濃といった具合に、両者の間には東西日本を分かつ大きなことばの壁がある(余談ながら、県境より少し西に食い込むが、恵那市三郷町に「だじゃの松」という東西方言の境界線を示す松と記念碑がある)。「そもそも信州の方言を知らない」という人が多いはずだ。
ここで想定している信州の方言の特徴は推量「~ずら、ら」で代表されるものである(信州北部は除く)。これは信州だけでなく、山梨、静岡と共通の特徴である(現在は「~だら」、もしくは共通語形「~だろ」に変化している地域が多い)。三河の「~だら」も元は「~ずら」だったという。先行研究によれば、東美濃の老年層が「~ずら」は使っていたという(「~ら」は現在もあり)。したがって「~やら」は「~ずら」の名残りと考えて間違いない。このように東美濃の方言は「信州と共通の基盤を持っている」と考えられる。
その一方、名古屋など尾張や西美濃との交流は深く、言語的にもその影響は顕著である。まとめれば、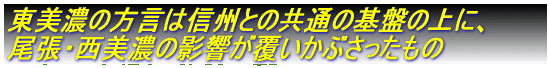 と言える。
と言える。
次頁ではそのような地理的特性の東美濃の歴史を考察する。
※ BBSでの まつさん によれば、東美濃と三河の民俗的共通点として
・豊川から勧請してきたお稲荷様が東美濃の寺にあり。
・正月には豊川稲荷にお参りする習慣もある
・”土雛”の流通範囲が共通
といったことがあるという。ここに記してお礼申しあげます。
 |
 |
| 多治見市内のオリベ・ストリート。伝統的な街並みを生かした界隈。東美濃の中心都市であり、美濃焼の代表的産地であるこの街には焼物関係の店舗や施設が多い。 |